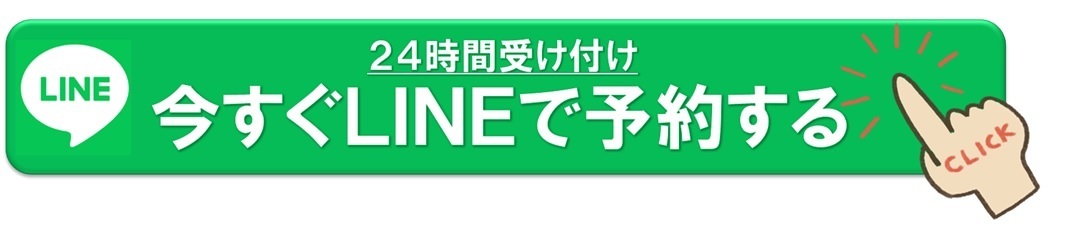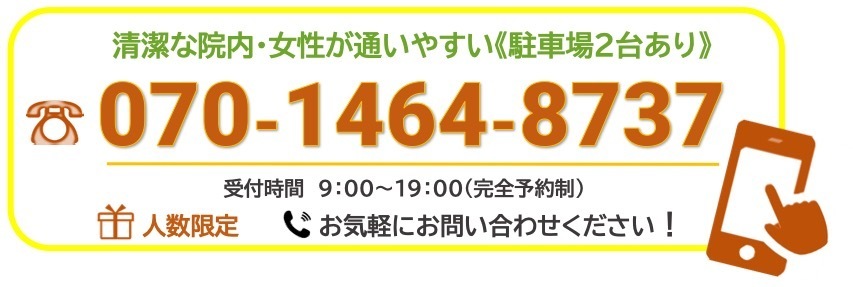今からできる花粉症対策をご紹介

こんにちは
整体院しん院長の今井です。
今回は前々回にお話しした。花粉症対策が非常に好評でした。整体に来る人も興味津々で、すごく気になっているようだったので、もう少し詳しく掘り下げて、花粉症の具体的な対策を説明していきます。
少し長い文章なるので、気になるところだけでも参考にしてみてくださいね。
前回は花粉症と乳酸菌、フラクトオリゴ糖についてお話しして腸内環境が大切と言うことを書きました。花粉症対策として腸内細菌もとても大切ですが、今から説明することも合わせてもらうと、さらに効果がアップします。
まず、花粉症を引き起こす1番の原因がヒスタミンと言う物質です。
ヒスタミンと言うのは、アレルギー反応が起こったときに、肥満細胞から放出される物質です。ヒスタミンがたくさん分泌されると、炎症が起こって鼻炎になったり、痒みが出たりして花粉症やアトピーのような症状が出やすくなります。
アレルギー反応として、ヒスタミンが分泌されること自体は悪いことではありません。むしろ体の防衛反応として出ているため正常と言えるのですが、過剰反応してたくさん分泌してしまうと辛い症状が出てきてしまいます。
病院に行って処方される薬は基本的にこのヒスタミンを抑える薬になります。
ただ薬を飲んだところで、押さえ込んでいるだけなので、花粉をたくさん浴びたり、ヒスタミンの放出が多くなる生活習慣を送っているとなかなか良くならないのです。
では、薬以外で、このヒスタミンの過剰分泌をどのように減らしていけば良いのでしょうか?
大切なこととしては、食事を見直すことと、生活習慣を気をつけること、2つの対策法があります
まず食事で花粉症対策をしていく場合は、以下の点に気をつけていきましょう。
✅ ビタミンDを摂取する
→ ビタミンDは免疫の暴走を抑えて、肥満細胞の安定化を助けると言われています。鮭・卵・きのこ類や、日光浴で補給可能。
✅ ケルセチン(ポリフェノール)を摂る
→ 玉ねぎ・リンゴ・ブロッコリーなどに多く含まれる成分で、ヒスタミンの放出を抑える。
✅ ヒスタミン分解酵素「DAO(ジアミンオキシダーゼ)」を増やす 。
→DAOはヒスタミンを分解する酵素。DAOを増やす食品:レバー・魚・ナッツ・ほうれん草・ビタミンB6(鶏肉・バナナ)
✅ ヒスタミンが多い食品を避ける
→ ヒスタミンを含む食品を減らすと、体内のヒスタミン量が抑えられます。発酵食品(チーズ・キムチ・ワイン)や加工肉(ハム・ソーセージ)
✅ 炎症を抑える食事(抗炎症作用のある食べ物を摂る)
→ オメガ3脂肪酸(青魚・アマニ油・エゴマ油)が、アレルギーの炎症を和らげます。カレーのスパイス「クルクミン」も抗炎症作用あり。
医学の父ヒポクラテスも、万病は食事から改善させるものであると言っています。食生活は私たちの体を作っているため、その影響が直接体に出ます。食生活が乱れて花粉症が出やすい身体になっていた人は要注意ですよ。
次に生活習慣についてどのように見直せばいいかお話ししていきます。以下のことに注意して生活をしてもらうと、花粉症が楽になる可能性が大幅アップ。
✅ ストレスを減らす(副交感神経を優位に)
→ ストレスが増えると、肥満細胞が活性化してヒスタミンを大量放出されます。深呼吸・ストレッチ・入浴でリラックスしましょう。
✅ 腸内環境を整える(腸は免疫の司令塔)
→ 腸のバリア機能が弱ると、異物(花粉)への過剰反応が強くなります。乳酸菌・ビフィズス菌・発酵食品・食物繊維を意識しましょう。
✅ 部屋の換気は短時間にする
→ 窓を開けるときは朝か夜に5分程度。昼間は花粉が多いので閉めましょう。
✅ 空気清浄機を使う
→ 花粉除去フィルター(HEPAフィルター)付きのものを選ぶと良いでしょう。
生活習慣としては、日々のストレスを減らし、免疫の低下を避けることと、花粉症に直接触れる機会を減らすことを意識していきましょう。
今回お伝えしたことに気をつけてもなかなか良くならないと言う場合は、舌下免疫療法や薬を使って抑えると言うのも1つの選択肢になってくると思います。
ただ今回お伝えした内容を意識もせずに薬ばっか飲んでいても、改善はなかなか見込めません。
食事や生活環境を見直してどれぐらい変化するかもぜひ試してみてくださいね。
※今回は、AIの力もお借りして記事を書きました。
自分の健康は自分で守る。
このブログは健康や身体の不思議など情報を発信しています。
しん先生のブログは毎週水曜・土曜に更新中。
次回もお楽しみに!