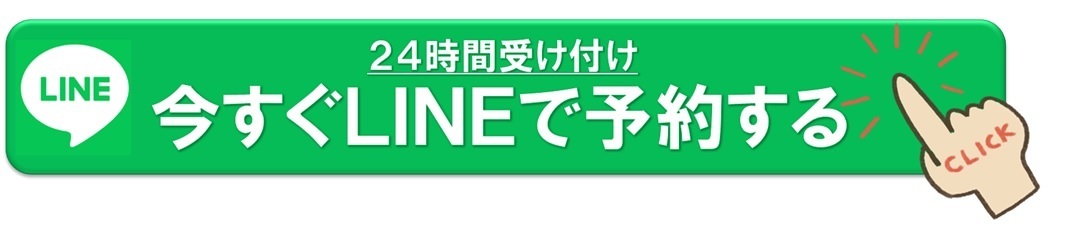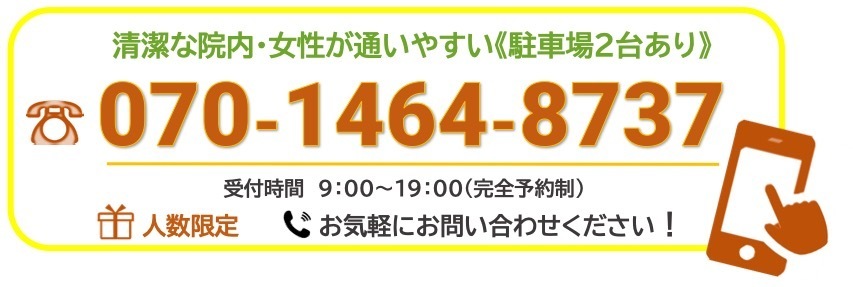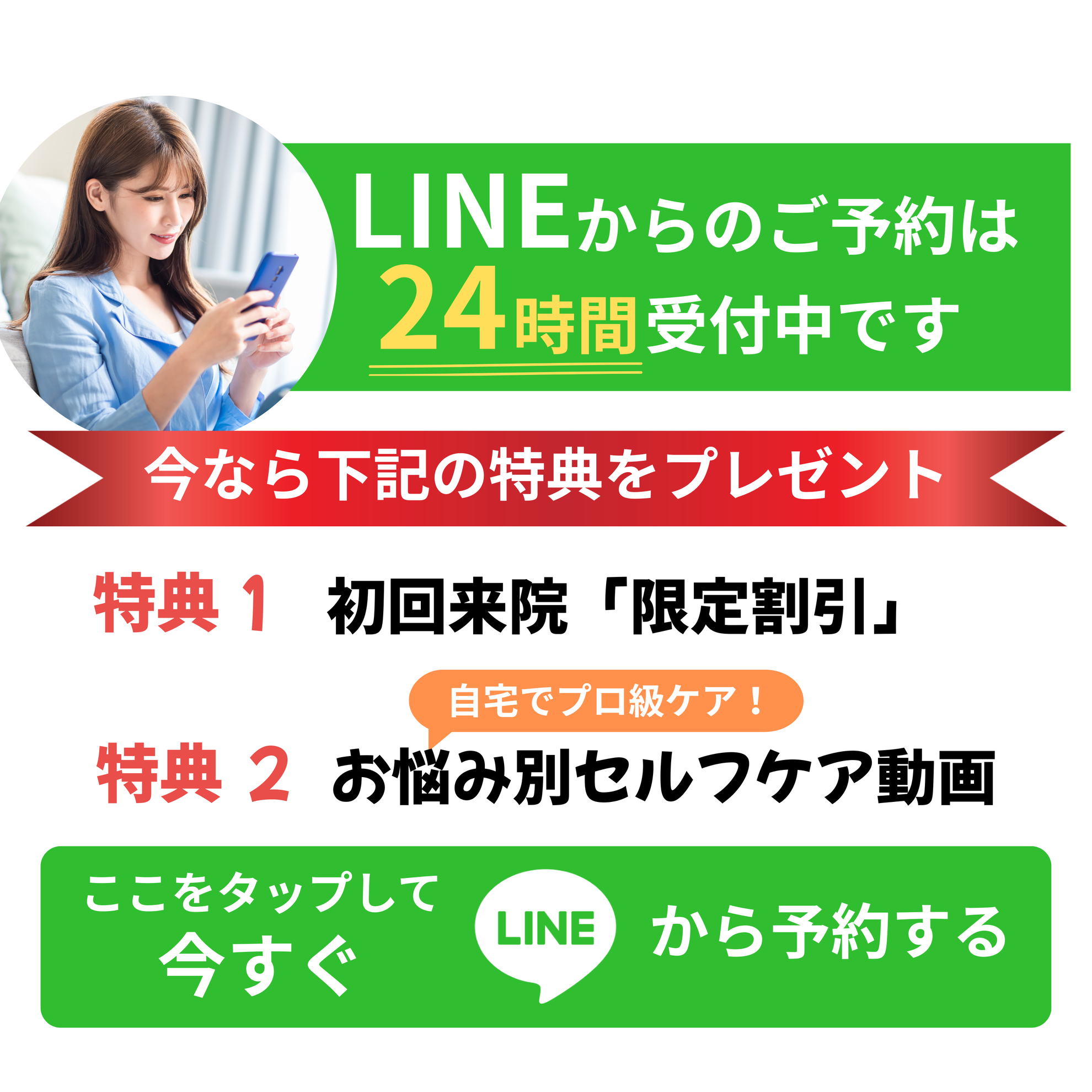呼吸法でできる秋の体調管理

こんにちは 整体院しん院長の今井です。
秋になると朝晩の気温がぐっと下がり、日中との寒暖差が大きくなります。この季節に「なんとなく疲れが抜けない」「風邪をひきやすい」と感じる方が増えるのは、実は自律神経の乱れや免疫力の低下、そして呼吸の浅さが深く関係しているのです。
自律神経は体温や呼吸、心拍を自動で調整してくれる神経です。私たちが意識しなくても体を一定に保ってくれるおかげで、季節の変化やストレスにも対応できます。しかし気温差が大きい秋は、体温を一定に保つために自律神経がフル稼働し、交感神経(緊張モード)が優位になりやすく、副交感神経(リラックスモード)とのバランスが崩れやすいのです。このバランスの乱れが、疲労感や免疫力の低下、睡眠の質の悪化といった不調の引き金になります。
特に秋は、気温の低下やストレスで肩や胸まわりの筋肉が緊張しやすく、呼吸が浅くなりがちです。呼吸が浅いと酸素の取り込み量が減り、エネルギー代謝や免疫細胞の働きが落ちてしまいます。特に胸郭や肋骨が硬いと、肺がしっかり膨らまず深い呼吸がしにくい状態になります。呼吸筋である横隔膜や肋間筋が硬くなると、酸素を取り込む力が低下し、体の疲れやだるさが抜けにくくなり、風邪や体調不良のリスクが高まります。
ここで少し専門的な視点を加えると、呼吸と自律神経は密接に連動しています。息を吸うと交感神経が働き、体は活動モードに。逆に、息を吐くと副交感神経が優位になり、体はリラックスモードになります。つまりゆっくりと長く息を吐くことは、自律神経を整えて免疫力を高めるうえでとても重要なのです。
また、最近では「寒暖差疲労」という言葉も注目されています。これは気温差が大きい環境で自律神経が酷使され、体が常に緊張して疲れが取れなくなる状態を指します。呼吸が浅いとこの疲労が回復しにくくなり、冷えや肩こり、頭痛などを引き起こす原因にもなります。
そこで大切になるのが、胸郭や肋骨の柔軟性を保ち、深い呼吸を取り戻すことです。ここからは、誰でも簡単にできるセルフケアを3つご紹介します。
-
肋骨ストレッチ
椅子に座り、両手を頭の後ろに添えます。息を吸いながら胸を大きく開き、肋骨が左右に広がる感覚をしっかり感じましょう。吐きながらゆっくり元に戻します。5回ほど繰り返すことで、胸まわりがほぐれて深い呼吸がしやすくなります。 -
腹式呼吸
仰向けに寝てお腹に手を当てます。鼻から息を吸い、お腹を風船のように膨らませるイメージで。口からゆっくり息を吐き、お腹がぺたんこになるのを感じます。1日5分だけでも副交感神経が働きやすくなり、リラックス効果が期待できます。 -
温めケア
首や背中を温めて寒暖差疲労を防ぐこともおすすめです。特に入浴は効果的で、38〜40度のお湯に10〜15分浸かると副交感神経が優位になり、心も体もリセットされます。
秋は気温の変化で体が揺らぎやすい季節ですが、深い呼吸と体の柔軟性を保つことが免疫力を守る大きなポイントです。呼吸を整え、自律神経をリセットしながら、季節の変化に負けない体づくりをしていきましょう。